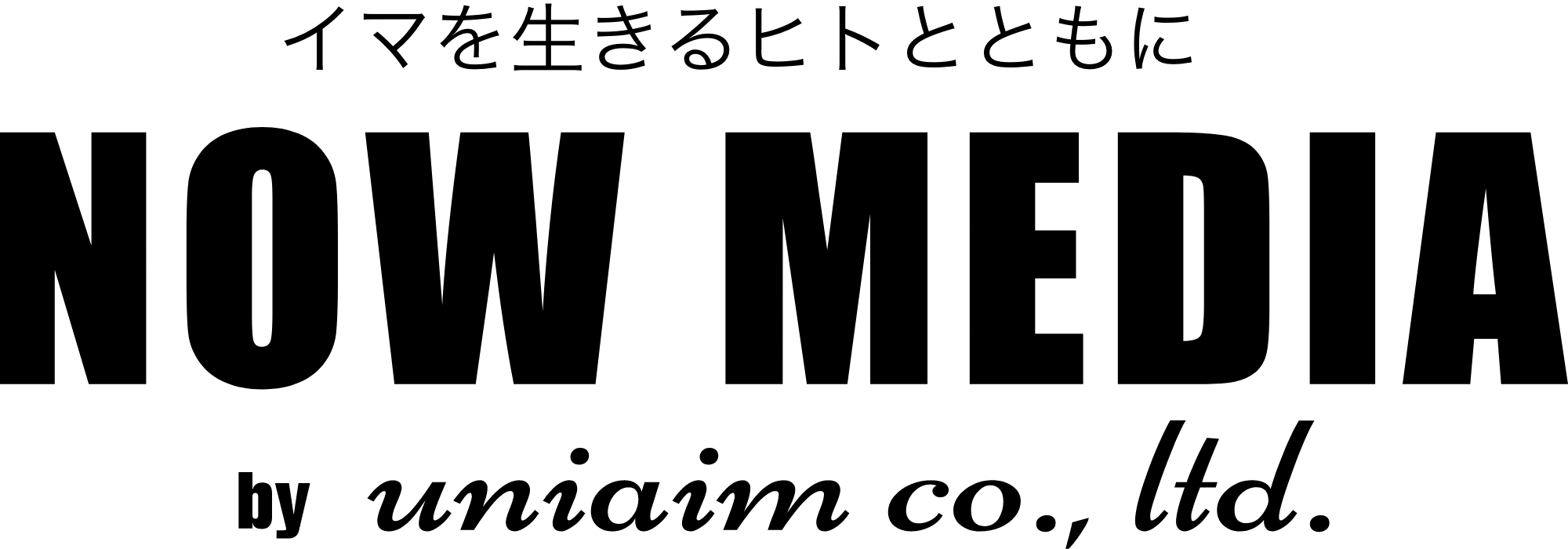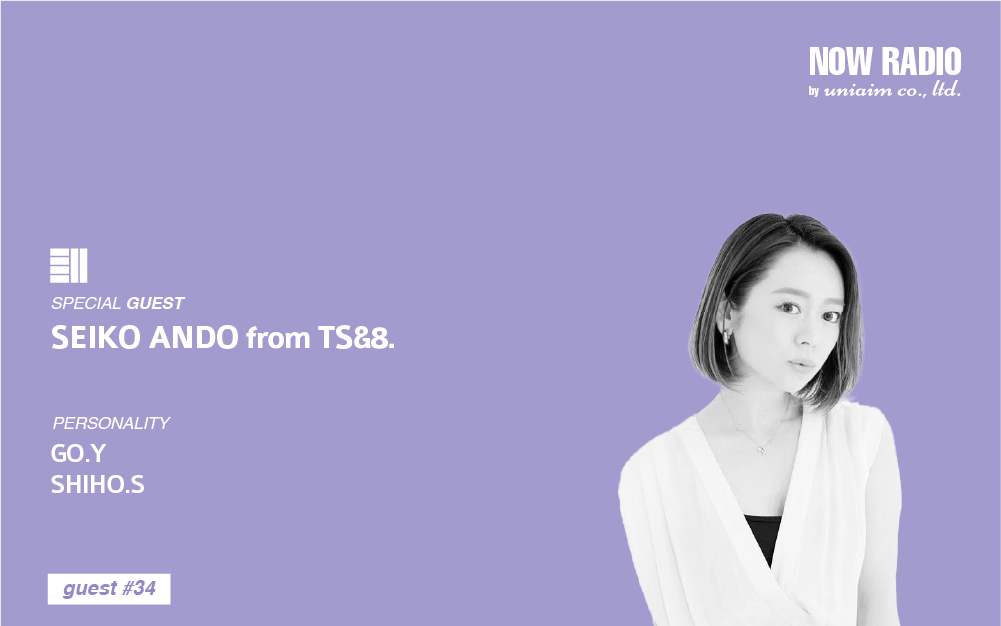GUEST INFORMATION
安藤 成子
株式会社Ts&8取締役
株式会社Ts&8 取締役
http://www.tsand8.com/
https://so-mensososo.com/
1:母娘起業
2013年に自身の母親と一緒に立ち上げた株式会社Ts&8の由来はお母様の名前の多恵美のT、自身の名前の「s」、安藤にかけた「&」、祖父、母親、自身の誕生日が8日から「8」をつけてTs&8と言う社名にしたそうだが、全てにきちんとストーリーがあるところがなんとも安藤氏らしい。立ち上げたきっかけは前編でも話を聞いたが祖母の実家が和菓子屋さんだったところから起業し代官山に和菓子と和食の1店舗目をオープンさせ、基本はメニュー考案を担当しているが、和菓子の職人に作り方を学んだこともあり一通りの和菓子は作れるそうだ。1店舗目をオープンした当時は安藤氏も母親もお店に立ち家族経営かと聞かれるほどにアットホームな雰囲気のお店だったが締めに出していたそうめんがきっかけとなり恵比寿に専門店を出店し今や10年でセントラすキッチンを構えるほどに大きく成長をした。親子経営は大変かを尋ねると「大変です」と、はっきり即答をしていたが、親子ゆえ周りが引くほどに激しい喧嘩をしても親子なので次の日にはケロッと戻れる、そこが他のビジネスパートナーではできない良い点でもあり、親子だからこそできる迅速な意思決定や、信頼関係の構築もあると続けてくれた。安藤氏が店舗プロデュースを担当し、母親が経営管理を担当し役割分担も明確にしている点もうまくいっている秘訣なのかもしれない。因みにお母様は現在も店舗に立ち夜中まで働いていると話し「止まったら死んじゃう回遊魚のようなエネルギーのある親子でやってます」と笑って教えてくれたが、2人とも事業を心から楽しんでいる様子がうかがえた。
2:増えていく第二の故郷
前編で香川県の小豆島の「島の光」というそうめんとの出会いについて聞いたが、400年も続く老舗との取引を決めるまではさぞ大変だったのではいかと聞くとやはり門前払いまではいかないが、安定しているしもうこれ以上労力もないと満足していると取り付く島もない感じだったと振り返った。しかし何度も足を運び説得をし熱意を伝えた結果、お取り組みが実現し今やと言う各地の手延べそうめんの組合の方が集まる「そうめんサミット」に安藤氏はゲストとして呼ばれるほどに手延べそうめんを盛り上げたいと言う気持ちが伝わり貢献するまでに存在感を発揮するとは流石である。他にも色々な地域に出向き食材の作り手さんと話すと現状に満足をしている方がいる一方で実は色々とやりたいがやり方がわからない方もいて、自分がそのきっかけになれれば嬉しいと感じているそうだ。そういった色々な地域の方と関わりを持つにつれ「第二の故郷が増えてきます」と素敵な表現をしていたが地元の方達にお帰りと言ってもらえるのは安藤氏の誠実さや真摯に向き合って取り組んでいる証拠でもあり賜物である。
3:そうめんを海外へ
自身の展望として日本の食文化、食材を世界に広げていき若い方に継承していきたいと、そして食のリノベーションカンパニーにしていきたいと話してくれた。リフォームではなく元々あるもの、素材に良いところを伸ばして新しくしていき新しい価値を作っていきたいと考えているそうだ。コロナ禍前にニューヨークで開催されたジャパンフェスに出店した際に流しそうめんを行い当初は口をつけた箸を水につけて共有することが受け入れられるのかと不安を感じていたがゲーム感覚で楽しんでくれている様子を見て、美味しいとたくさん食べてもらえてくれた時に手応えを感じ海外に絶対お店を出したいと意欲を示してくれた。逆に日本国内で今、注目している地域や食材を尋ねるとセントラルキッチンがある五島列島には綺麗な海にいる魚や、海風のミネラル豊富な土壌で育った野菜など豊富な食材、特に手延べそうめんと同じく職人が一つ一つ手で伸ばしていく五島列島の食材を使った五島うどんの可能性について紹介してくれた。「今度はうどん?」と茶目っけたっぷりに笑いながら話していたがきっともう構想があるのであろう、明言はしなかったが何かを見据え先に進んでいるような気がした。その自身のパワーの源は「人に会うこと」だと話し、その地域ごとの悩みや成功例など色々な話を聞きアイデアへのヒントが原動力になっているそうだ。2024年は色々なアイデアを温める守りの年だったが2025年はそれを放出する年にしたいと締めくくってくれた。
安藤氏は自身を「食のリノベーションをしている」と表現し、まだ知られていない美味しい食べ物や食材に出会うとどうにかしてあげたい、勿体無い、もっとたくさんの人に知ってもらいたい、では私はどうすればいいかと語る姿は、伝統的な日本の食文化の継承と革新をする伝道師のようだと思った。それも現代的にアレンジをしネーミングセンスに溢れ、食欲と興味をそそる達人でもある人。今後もきっと私たちに慣れ親しんでいるがちょっと地味な存在の“アレ”をアップデートした新たな日本食を提供してくれるだろう。安藤氏が目をつける“アレ”が次は何でどんな風に変わって現れるのか楽しみである。