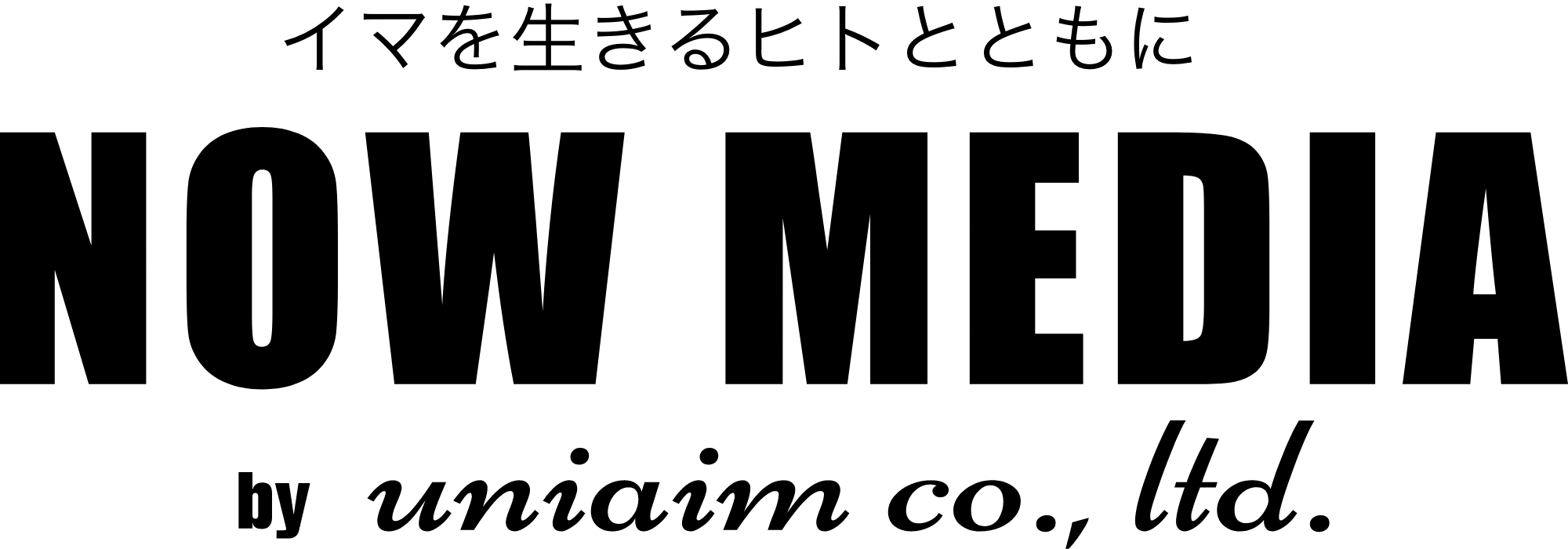GUEST INFORMATION
渡部 郁子
温泉ソムリエ / アウトドアナビゲーター
温泉ソムリエ / アウトドアナビゲーター
https://miraihouseworks.com/
アウトドアナビゲーター/温泉ソムリエ。学習院大学法学部卒。旅行会社、局アナを経てフリーに。JFNなどでアウトドア番組を担当し、All Aboutガイドとして執筆。山と温泉、音楽の魅力を親子で楽しむスタイルを提案。著書『東京温泉ナビ』(2025)刊。株式会社みらいハウスワークス代表。温泉療養士資格を持ち、渋谷のラジオでニュース番組も担当。取材・講演、メディア出演多数。東京都在住。自然の楽しみ方発信。
1:東京温泉ナビ
前編の最後に少しご紹介した渡部氏の著書「東京温泉ナビ」について詳しく聞かせてもらった。2012年に出版した「東京温泉案内」から10数年を経て、都内の温泉事情が変化したため、改めて取材し、掲載施設数を38から100に増やした超大作で、記念日などに利用したい特別な宿から、日帰り温泉が楽しめる施設充実型のところや、島嶼部(とうしょぶ)という東京の島にある温泉、温泉が使用されている銭湯、番外編として大流行中のサウナも少し紹介するなど盛り沢山の内容となっている。その中でも特に注目したいのが東京の島嶼部、伊豆諸島の9島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島)と、小笠原諸島の2島(父島、母島)の計11島からなる地域なのだが、リゾート型施設とは対照的に無料の温泉も多く、地元の人々が集まるのどかで素朴な雰囲気や、自然に囲まれて泉質もよく季節によっては比較的空いているなど魅力的な要素が沢山あるにも関わらず、知る機会がないと行きづらく東京から近い距離でありながら行く人が少ないことから紹介を決めたそうだ。海が目の前に広がるロケーションは海に入った後に温泉を楽しめたり、西側に温泉があることが多いため綺麗な夕日を眺めてゆっくりと温泉に浸り夜は星空を眺めるなど非日常的な体験ができる点も島ならではではないだろうか。そして、最近の銭湯ブームにちなみ温泉を使用した銭湯も紹介している。よく見ると温泉分析表や泉質などの説明が貼られているところもあるが温泉なのか温泉じゃないのかという違いすら、我々一般の人にはなかなか見分けが難しい部分もあり特筆してくれるのはとてもありがたい。家とは違い大きな湯船に浸かるという銭湯の醍醐味に加え温泉の効果を得られるのであれば温泉を使った銭湯に行きたくなる。ちなみに都内で使われる温泉は黒湯と呼ばれる弱アルカリ性で黒湯に含まれるフミン酸などの有機物が、肌をなめらかにし、保温効果を高めると言われている。また浅い所から湧き出しているため温度も低くゆっくり浸かれるという利点も。蒲田駅周辺には黒湯を使った銭湯が軒を連ねているそうなので行ってみてはいかがだろうか。
2:温泉事情
日本には各地に温泉街があり、地域の高齢化や建物の老朽化、観光客の減少でシャッター街になっている場所もニュースなどで取り上げられご存知の方も多いはずだ。歴史がある分、長い年月を経て色々と問題が生じてしまうことは否めないが渡部氏は「二極化が進んでいる」と話す。人気の温泉地はオーバーツーリズムで混雑し、そうでない場所は人が少なく、星野リゾートのようなブランド化戦略や海外ブランドの参入により、個人経営の旅館は厳しい状況にあると指摘。情報を簡単に入手することができるようになり顧客が団体旅行から個人旅行へとシフトし選べるようになったことから「どこでもいいから温泉に行きたい」という時代は終わり、情報重視時代の昨今の風潮に伴い、サービス以外にもこれからは気分によって泉質で選ぶようになる、だからこそ温泉業界は温泉の泉質をPRし、ファンを増やすことが重要であると続けた。例えばあるお客様がお湯がぬるぬるしていると感じる場面があったとする、それをこれはアルカリ性単純温泉という泉質で肌の余分な脂や汚れを溶かしている証拠ですよと説明ができれば納得をしてくれるはずだが、説明ができないと不衛生なお湯と捉えられリピーターにはならないだろう。ましてや口コミやSNSで書かれてしまえばあっという間に噂が広がり新規客の獲得も難しくなってしまう。同じく湯花と呼ばれる天然温泉に含まれる成分が沈殿、固形化したものが湯に浮いていてそれを見た人が汚いと感じ、施設側が循環ろ過をせずに新鮮なお湯をそのままお客さんに提供したい、そのままの状態を楽しんでほしいという思いを説明ができずきちんと伝わらなければ真逆の垢やゴミが浮いた不衛生な温泉と捉えられてしまうかもしれない。他にもお湯の供給量を計算しきちんとお湯が回り切るか、綺麗なお湯を循環させるように緻密な設計をしているが、掛け流しじゃないからと選択肢から外されてしまうケースもあるという。兎にも角にもこれからは正しい情報の発信と発言ができるか、そこが要になっていくと力強く話してくれた。
3:温泉分析表とトレーニング
温泉に行くと効能などと一緒に「温泉分析表」を目にしたことがある人も多いはずだ。理科や化学の授業で聞いたことがあるようなカタカナに小文字の英語そして数字が並び、それを見て「なるほどこういう成分なのだ」と思う人はごく僅かだと思う。この温泉分析表は温泉に来た人が必ず見える場所に掲示しなければいけないという義務があり提示していないと罰金などの罰則があったり、時間の経過とともに変化する可能性があるため、定期的な再分析と掲示内容の更新が推奨されているため10年経過したらまた調べ直し張り替えなければならないなど実はとても細かく決められている。これを読み解くには至難の技ではと思ってしまうが渡部氏の著書に詳しく記載されており温泉ナビゲーターを受講すると詳しく教えてくれるそうなのでもっと温泉に詳しくなりたい方や成分で温泉を選ぶなどワンランク上を目指す方にはお勧めしたい。成分も大事だが入浴の時間帯は影響するのかを最後に尋ねてみた。お湯の成分は時間によって変動することはないが、朝は熱めの温度にすることでシャキっと目が覚め、夜は副交感神経を働かせるぬるめの温度でゆっくりと入ると熟睡ができる、また毎日湯船に浸かることでジョギング相当の運動量に匹敵するためトレーニングをしていることに繋がり体力がつくので、免疫力も向上すると教えてくれた。疲れているからシャワーで済ませてしまうと深部体温が下がりどんどん免疫力も下がってしまうと指摘した。短い時間でも湯船に浸かるトレーニングを欠かさないようにしようと思った。
日本特有であり素晴らしい文化の温泉に対してここまで真摯に向き合っている人に正直出会ったことがなかったが、柔らかい口調と分かり易い説明をしてくれたことでこちらも何故か温泉に詳しくなった気になってしまった。次回温泉に行くときは間違いなく効能を調べ、泉質を見てしまうだろう。人気の温泉地に行くも良し、新しい土地を開拓するも良し、自分のお気に入りを見つけるという楽しさもできた。何より自然本来の温泉を楽しみつつ守っていきたいと思った。
是非、渡部氏の著書を片手にいろいろな温泉へ足を運んで欲しい。