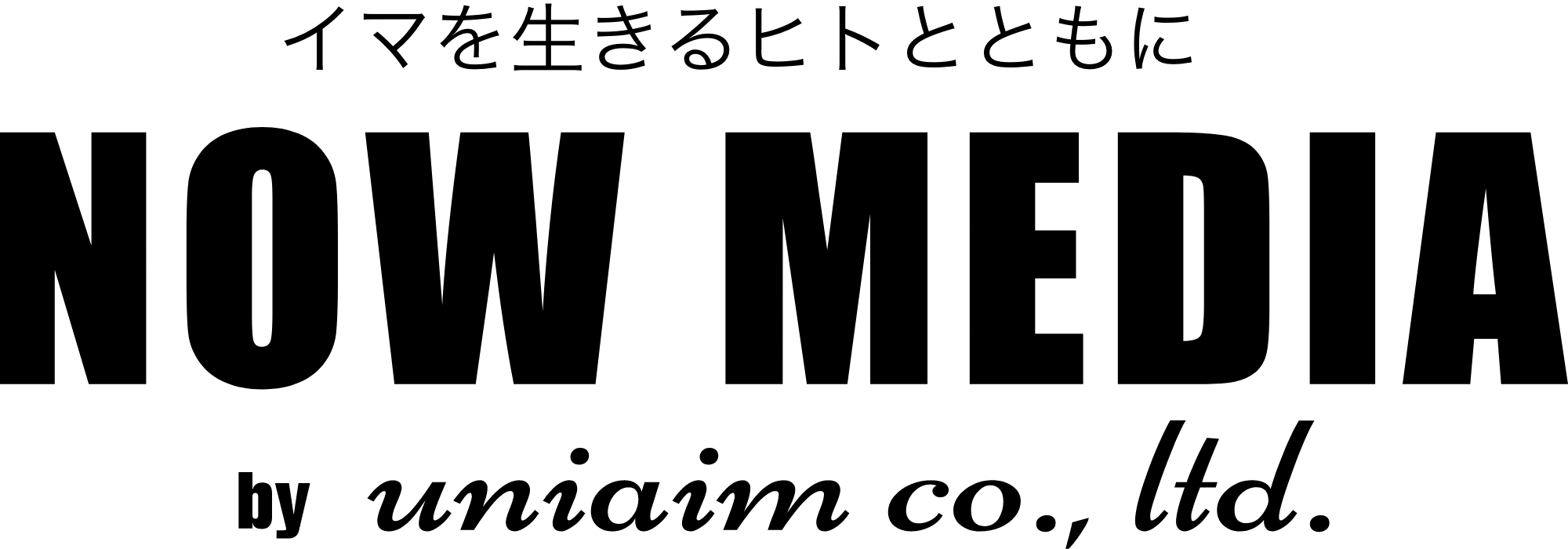GUEST INFORMATION
兵藤 慎剛
早稲田大学ア式蹴球部監督
早稲田大学ア式蹴球部監督
https://www.waseda-afc.jp/
長崎県出身。
1985年7月29日生まれ
国見高校時代、全日本ユース選手権、インターハイ、高校選手権の三大タイトルを獲得。
早稲田大学入学後は、東京都1部リーグからスタートだったが、1年次に関東リーグ2部昇格、
2年次に関東リーグ1部に昇格し、4年次にはキャプテンとして大学選手権優勝。
在学中、U-20日本代表でもキャプテンとして日の丸の10番を背負い、
ワールドユース選手権に出場しただけでなく、全日本大学選抜として2度ユニバーシアード世界大会
に出場し、金メダル獲得にも貢献。
卒業後は横浜F・マリノスでプロとしてのキャリアをスタート。
北海道コンサドーレ札幌、ベガルタ仙台、SC相模原に所属し14年間のキャリアを終え、
2023年から早稲田大学ア式蹴球部監督に就任。
1:学びと教え
兵藤氏のキャリアにとって後に大きな影響をもたらした国見高校時代、本人もすごくいい時代だったと言うように大久保嘉人氏が大きな功績を残しその翌年、翌々年も素晴らしい選手が集まり競合国見高校と呼ばれ正に黄金期に兵藤氏も選手としてプレーをしていた。同時にめちゃくちゃキツかったと振り返るようにその練習法、練習量は有名で、朝起きてからもご飯を食べてからも、試合で負けても勝っても体力の限界まで兎に角、走っていたそうだ。体力面だけでなく、普段の寮生活でも1年生、2年生、3年生の4人で部屋が割り振られ1年生は練習に加えて先輩の洗濯、部屋と寮の掃除も全てやり自分の時間はなく精神面での鍛錬も積んでいた。その厳しさに耐えたからこそ多くのことを学び仲間意識が芽生えチームプレーに繋がり全日本ユース選手権、インターハイ、高校選手権の3タイトルを獲得する。その後、早稲田大学へと進むのだが高校時代の恩師である小嶺忠敏先生と進路相談をする中で「プロは無理だ。足りない」と言われるがそれに反発せずに素直に受け入れたのは小嶺先生が大久保嘉人氏然り高校卒業からプロもしくは大学進学を勧める見極めが素晴らしいゆえ、しっかり大学で学びなさいと送り出してくれたと感じ取り早稲田大学で1回優勝してからプロにいこうと決心できたそうである。その後、早稲田大学在籍中には、関東リーグ2部から1部への昇格を果たし、最終学年で大学選手権優勝を達成。U-20世代別日本代表として世界大会にも出場し、世界の壁に直面する。世界トップクラスの選手はスピード、判断力、全てのアスリートとしての能力が圧倒的だったが特にオランダの選手はスピードがずば抜けており衝撃を受け2~3ヶ月オーバートレーニング症候群のような燃え尽きた状態になってしまい体が思うように動かず少し走っただけで息が上がりプレーが全然できなくなりサッカーとの距離を置くために2週間ほど練習も一切せず休んだ時期もあった。そこから楽しくサッカーをする自分の原点からスタートしようとマインドを変え少しずつ自分を取り戻していった時期にユニバーシアードの監督から声がかかりもう1回世界と戦うチャンスをくれた結果、世界一獲得という大きな経験をさせてもらう事となる。
2:2人の監督との出会い
卒業後は14年間Jリーグで計4チームに所属し活躍を果たすがその中でも特に横浜F・マリノスでの9年間の経験が印象深いと話してくれた。このチームで引退しやり切りたいと思えるほどに成長をさせてもらい、天皇杯での優勝、プロとしてタイトルを獲った経験全てが思い入れがあると振り返った。その後、現役を引退し自身も監督になるのだが、印象深い指導者を尋ねるとやはり、国見高校の小嶺忠敏先生だと即答であった。小嶺先生との出会いがなかったら間違いなく今の自分のキャリアはなく、今の監督業でも先生の教えが原点であり人間教育の点も含めて存在が大きいそうだ。サッカーの戦術面で衝撃を受けたのは、横浜F・マリノスから移籍した北海道コンサドーレ札幌に在籍していた時代のミハイロ・ペトロヴィッチ監督を挙げた。サッカーの監督は決まりごとの多い守備を初めに落とし込む事が多いが、ミハイロ監督は攻撃に関する教えが論理的でこうやったらこうなるときちんと落とし込んでくれてその通りにゴールが決まることが多かったそうだ。兵藤氏が移籍した1年目は残留することが目標で守備に力を入れていたためボールを相手側が60%コンサドーレが40%の割合で持たれることが多かったが攻撃に力を入れていたミハイロ監督に代わったことで相手側が45%コンサドーレが55%位の割合に変わり選手たちも大幅に成長し結果も出たそうだ。その攻撃を重視する戦術は今も大いに影響していると話してくれた。この2人に出会えた巡り合わせは本当に運が良かったと噛み締めていた。
3:学生主体の運営
サッカー選手にとって何よりもパワーのなるのがサポーターからの応援だと話すようにスポーツ競技の中でもサッカーは歓声がひときわ大きい印象を受ける。サポーターそうしも選手同様に戦っているそんな気さえも感じてしまう。兵藤氏も早稲田大学ア式蹴球部の試合を観ている人が楽しいと思ってくれるような展開したいと思い、躍動感のあるサッカー、常に全力を出し上手いとか下手ではなく一生懸命やっている姿こそが人の心を動かす上で大事なことだと、そこを観て欲しいと伝えてくれた。また、昨年の新国立の早慶戦では運営をほぼ学生が中心となりで開催され、観客を1万人以上入れて成功を果たしたそうだ。西東京市の東伏見にグラウンドがありここの運営も学生が行なっているとのことなので是非、足を運んでいただきたいと思う。
大学サッカーの一体感や、これからのサッカーをよくしようと奮闘する若者たちを応援していきたいと思った。
「臨機応変と言うと何をやっても良い集団になってしまう」と兵藤氏が言っていた事が非常に印象的で、臨機応変に考えて行動するようにと言われ、自分で考え行動してきた世代としては「何をやっても良い」と言う考えや選択肢は少ないのではないだろうか。それが現代では逆の解釈にもなり得るのだと驚いたが、学生に寄り添うという言葉よりも、合わせるという方が適切な気がして何だかどちらが指導者なのか少々の違和感さえ感じてしまったが、それが現代の正しい指導法なのかもしれない。これは学生に限らず社会人に向けても大いに参考になる指導方法なのではないだろうか。指導法も時代によって変わり、指導者は時代によっての「適切」を理解し言動を変えていく。耳が痛い大人たちも多いと思うが社会も個人プレーではなくチームプレーであるということ、それが現実であるのだと痛感した回であった。