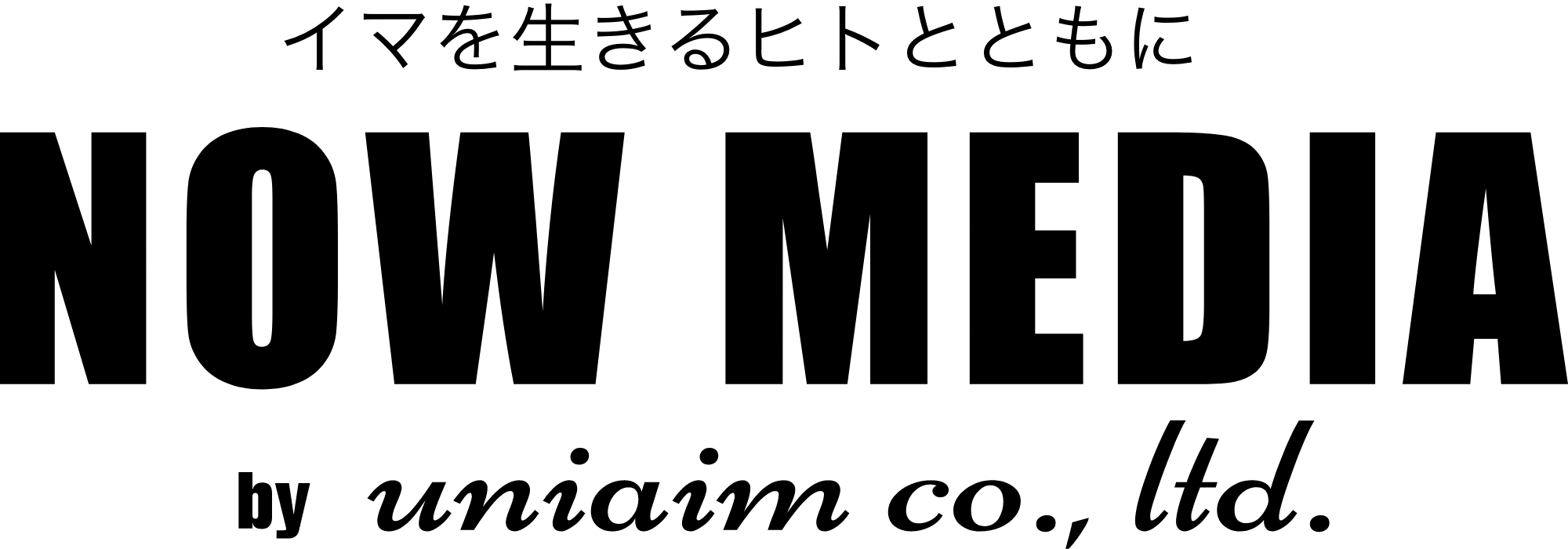GUEST INFORMATION
兵藤 慎剛
早稲田大学ア式蹴球部監督
早稲田大学ア式蹴球部監督
https://www.waseda-afc.jp/
長崎県出身。
1985年7月29日生まれ
国見高校時代、全日本ユース選手権、インターハイ、高校選手権の三大タイトルを獲得。
早稲田大学入学後は、東京都1部リーグからスタートだったが、1年次に関東リーグ2部昇格、
2年次に関東リーグ1部に昇格し、4年次にはキャプテンとして大学選手権優勝。
在学中、U-20日本代表でもキャプテンとして日の丸の10番を背負い、
ワールドユース選手権に出場しただけでなく、全日本大学選抜として2度ユニバーシアード世界大会
に出場し、金メダル獲得にも貢献。
卒業後は横浜F・マリノスでプロとしてのキャリアをスタート。
北海道コンサドーレ札幌、ベガルタ仙台、SC相模原に所属し14年間のキャリアを終え、
2023年から早稲田大学ア式蹴球部監督に就任。
今回お迎えするゲストの兵藤 慎剛氏の経歴を紹介すると国見高校時代に全日本ユース選手権、インターハイ、高校選手権の三大タイトルを獲得、早稲田大学入学後は、東京都1部リーグからスタートするが1年次に関東リーグ2部昇格、2年次に関東リーグ1部に昇格し、4年次にはキャプテンとして大学選手権優勝。在学中、U-20日本代表でもキャプテンとして日の丸の10番を背負い、ワールドユース選手権に出場しただけでなく、全日本大学選抜として2度もユニバーシアード世界大会に出場し、金メダル獲得にも貢献。卒業後は横浜F・マリノスでプロとしてのキャリアをスタートし、北海道コンサドーレ札幌、ベガルタ仙台、SC相模原に所属し14年間のキャリアを終え、2023年から早稲田大学ア式蹴球部監督に就任。輝かしい現役時代から現在の監督としての意識の違い、想い、展望など話を聞いた。
1:サッカーで教えられる指導者
兵藤氏の経歴は冒頭でお伝えした通りだが、サッカー部ではなく聞き馴染みのない「ア式」について説明するとア式とは、サッカーの別称である「アソシエーション式フットボール」の略で、大学サッカー部などの部名として用いられ、現在はこの名称を部名に揚げているのは大学サッカーでは伝統ある早稲田大学、一橋大学、東京大学の三大学のみとなっている。早速、現役引退後から監督就任の経緯を尋ねると、2022年に現役を引退後「1年間ニートをしていたんです」と答えてくれたが、もちろん俗に言うニートとは少々意味合いが異なりフラフラとしていた訳ではなく、自分が何をやりたいのか、何に向いているのか、何にエネルギーを注げるのかを模索していた1年間だった。出身の長崎で部活動やスポーツがどのように教育に関わっているのかを勉強し、北海道では兵藤氏が自分の価値観を変えてくれたと表現する人のもとで活動をしていた時に、たまたま早稲田大学のOBの方から「監督をやらないか」と、連絡がくる。引退後のキャリアの中で指導者も選択肢の中で思い描いていたこともあり、しかも自分の母校でもある早稲田大学でチャレンジできる、こんなチャンスはそうない事だと思い承諾をしたそうだ。現在は監督就任3年目になるが、就任1年目はチームが関東1部リーグから2部へと降格し、2年目はその反省点やアプローチの仕方を変えたりと色々とやってみたが“勝ち点2”の壁に阻まれ昇格を果たせず悔しい年となった。現在80人ほどが在籍している部員には、監督就任から2年が経ち少しずつ「兵藤イズム」が入ってきていると実感しているそうだがそのイズムとは?を聞くと「気持ちが大事」と即答してくれた。うまければいいと技術的な部分だけではなく「人としての強さ」それこそが早稲田であり、そうあるべきで目指していると続けてくれた。兵藤氏の国見高校時代の恩師である小嶺忠敏氏が人間教育、人間力をテーマに挙げ育ててくださったと言うように高校時代に気づけなかった事が年を重ねるにつれありがたみが分かり、サッカーの技術や戦略も大事だがやはり人としてどう生きるかの方が圧倒的に大事だと言うことをサッカーを通じて学べる、それを伝えていきたい、サッカーを教えられる指導者を目指すのではなく、”サッカーで”教えられる指導者になりたいと力強く話してくれた。
2:イズムの継承と進化
就任した3年前に在籍していた学生たちの能力は相当高く早稲田史上最多のプロ入りが7人もいたそうだが一部リーグの中では最下位のチームでもあった。つまりは個の能力が高くとも1+1が2以下になることの多いスポーツゆえに1+1が2以上になるには組織としての強さが重要となる。そこを個人が意識しないとチーム全体が強くなることはなくチームスポーツの永遠のテーマではあるがそこが足りていなかったと感じ、1+1が2以上になるようにしていったところ本質的に理解してくれる学生が多くなりチームスポーツとして勝つことを表現できるようになってきた。その結果、2024にはプロ入りした選手が3人いたと自らの力で勝ち取ったと嬉しそうに話してくれたのが印象的だったが、監督の意図を本質的に掴みチームに必要な選手だということがプロでは大事な要素でもあると厳しい視点も覗かせた。学生に対しては期待も込めてだがすぐにレギュラーが取れるかと言ったらそれは間違いなくそうではない必ず壁にぶち当たる、最初から出れるほど甘い世界ではないから学びの姿勢を忘れないこと、自分の良さを見失わずにチームの良さを活かすためには自分はどうできるかをちゃんと考えなさいと学生たちにも伝えているそうだ。それは兵藤氏がプロで戦ってきたからこそ見える部分でもあり実体験からの学びでもあるが「大卒は高卒と違ってだいたい即戦力の枠なんです。もう育成じゃないんで」と非常に刺さるフレーズを交えながら説明をしてくれたが、ある程度勝負をさせてもらえるチャンスがあり、勝ち点を稼ぎ取ってくれる選手が集まっているのがプロでありチームを勝たせられる人が間違いなくプロの世界で長くサッカーを続けらる人だよと、技術云々よりも勝たせられることに対して自分が何をできるかを常に考えなさいと伝えている。「兵藤イズム=人間力」をどうやって自分の中で理解し消化をし実践していくかそこからまた新たなイズムが生まれるのかもしれない。
3:自由度の違い
プロの世界では全員が全員、自分の武器を知り誰よりも自分が優れている、型にハマろうとせずに自分のスタイルはこれだと尖っている人ももちろん必要だが、協調性が高く上手くまとめられる人も同じく必要で、そこをバランスよく中和してくれるのが監督である。その中で兵藤氏曰く、自分の居場所がどこかを感じ取り表現をしないといけない、その難しさを深く考えれば考えるほどに沼にハマっていく感じがあるそうだ。その準備として兵藤氏は、4年生になるキャプテンを含めた学生たちにどういうチームでどういう風に進めていきたいかを話し合ってもらい一任しまとまったことを自分に提案してもらっている。最高学年の4年生と監督が話し合いながら決めていくスタイルが2024年に100周年を迎えた早稲田大学ア式蹴球部の伝統でありOBが築き上げてきた早稲田大学の哲学「早稲田・ザ・ファースト」が根幹にあり、サッカーだけではなく人としても一流であれ、一番であれという教えにも結びつく。伝統を重んじる中で自身の学生時代と現役の学生で違いはあるかを聞くと「今の学生は髪の毛染めている子はいないけど、自分たちの頃は髪の毛を染めて良かったんですよ」と面白い回答が返ってきた。なんとも男の子らしい発想だと思ったがその感想とは裏腹に実に面白い話が聞けた。兵藤氏の学生時代にはピッチ上100%を出せばそれ以外は自由にやっていいよという教えだったからこそピッチ上で全てを出せないと試合に出してもらえない、そのためには何をするか何をするべきかを自らが考える。その代わりに自由を与えてくれるからこそピッチ上では誰にも負けないとピッチ上で喧嘩もするほど熱くサッカーに向き合っていた。しかし、現代の学生たちは情報がすぐに手に入り技術レベルそのものが上がってきているが情報ベースだからこそ応用がきかず、情報だけを持っていてその場で何をしたら良いかが生まれない応用が利かないそうだ。ある学生がずっと攻め続け相手側のゴール前に10人の守備が立ちはだかった、その時に攻撃をしていた学生がグランドの中から「ここからどうすればいいですか?!」と試合中に質問が来たそうだ。正直、え!?と思ってしまうエピソードであるが現代の子にとっては答えを自ら導き出すのではなく答えをすぐに求める癖がついているのかもしれない。疑問に思ったことはネットで調べればすぐに答えが見つかる、だが今は試合中だから調べるわけにはいかない、だから監督に聞く、それが最短の答えであるからだ。ある程度の想定では動けるが想定外の状況は教えてもらっていないからどうしていいか分からない、自由に楽しくどんな発想でも良いからと指導してきたはずが答えを簡単に求める姿勢にとても悩まされたそうだ。更に、早稲田としてはこうしたいからこうしていこうと優先順位をつけないと何をしても良いと言ったじゃないですかとなってしまう、サッカーを噛み砕いてどこまで伝えるべきか、どこまで自由度を与えた方がいいのかを見極め考え方の基準を定めることが必要だと感じたのが2年目だったと振り返り、学生側も話がしやすい環境を作ってあげることも大事だとと話してくれた。
前編では兵藤氏の現在を聞いたが、兵藤イズムの原点は何か、今後の展望は何かを中心に聞いていこうと思う。